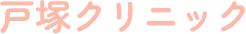2025/10/02
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
🏥 オレゴンのメディケアと日本の高齢者医療費 – 実際の負担はどちらが重い?
✈️ 序章 – 米国で受けたカルチャーショック
2024 年秋、私はオレゴン州に住む 70 歳の友人を訪ねました。友人はカイザー・パーマネンテの メディケア・アドバンテージ(Senior Advantage) プランに加入しており、そこで耳にした話は、私が抱いていたアメリカの医療制度のイメージを覆すものでした。
-
RSV ワクチン、組み換え型帯状疱疹ワクチン(シングリックス)、COVID‑19 ワクチン、インフルエンザワクチン を接種したそうですが、友人によれば自己負担は一切なかったとのことです。これらのワクチンは日本では自費扱いが基本で、インフルエンザなら 1 回 3,000〜5,000 円、シングリックスや RSV ワクチンは 1 回 2 万円以上と高額です。
-
プライマリーケア医への受診料は無料で、専門医でも数十ドル程度、年間の自己負担額には上限があると聞きました。
一方、日本では 2025 年 8 月から高額療養費制度の上限が引き上げられ、2025 年 10 月には 75 歳以上の一部高所得者の医療費窓口負担が 1 割から 2 割に上がります。テレビでは「日本の高齢者の自己負担は安すぎる」「負担が軽いから無駄に受診する」といった論調も見かけます。本当に日本の医療費は安いのでしょうか。オレゴンで見聞きした実例と日本の制度を比較し、ワクチン費用や自己負担の実態を考えます。
🇺🇸 オレゴン州のメディケア・アドバンテージ(カイザー Senior Advantage)
💉 ワクチンが無料になる仕組み
米国の高齢者向け公的医療保険 Medicare は、民間保険会社が提供する メディケア・アドバンテージ(Part C) を選択することができます。2023 年のインフレ抑制法により、成人向けワクチンのうち ACIP(米国免疫諮問委員会)が推奨するものは、メディケア加入者の自己負担がなくなりました。カイザーのプランでは Part D のティア 6 に分類されるワクチンが 0 ドルとなっており、RSV、シングリックス、インフルエンザ、COVID‑19 などのワクチンは薬局や医療機関で無料で接種できます。友人が複数のワクチンを無料で受けられたのはこの制度のおかげです。
💵 診察費と年間自己負担上限
カイザー・Senior Advantage には Value、Standard、Enhanced の 3 プランがあり、月額保険料は 0〜114 ドル、免責額はゼロです。プライマリーケア医の受診は無料で、専門医でも 20〜35 ドル程度です。入院費はプランによって 1 日 200〜275 ドル程度が 6 日目まで課され、それ以降は無料になります。年間自己負担上限(MOOP)は 3,000〜5,000 ドル に設定されており、この上限に達するとその年はそれ以上支払う必要がありません。
| プラン名 | 月額保険料 (USD) | 年間自己負担上限 (USD) | 入院費(初日〜6日目/日) | 専門医受診料 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Value | 0 | 5,000 | 275 | 35 |
| Standard | 28 | 4,175 | 250 | 30 |
| Enhanced | 114 | 3,000 | 200 | 20 |
❤️ バイパス手術費用の比較
友人は以前、カイザーの保険下で冠動脈バイパス手術を受けました。入院は 3 泊 4 日で、Standard プランでは 1 日あたり 250 ドルの入院費がかかります。4 日間で約 **1,000 ドル(約 14 万 8 千円)**です。これに医師の診療費や検査費が加わっても、年間自己負担上限 4,175 ドルには遠く及ばないため、**実際の自己負担額は 1,000 ドル前後(ただしその年の他の医療費次第では数百ドルで済む場合もある)**でした。手術そのものの費用は数万ドルと言われますが、保険と政府補助により患者の負担はごくわずかです。
日本で同じ冠動脈バイパス術を受ける場合、手術費用は約 300 万円ほどかかりますが、高額療養費制度により患者の自己負担額は大きく抑えられます。70 歳以上の一般的な所得層では月あたりの自己負担上限が 57,600 円(年間 144,000 円)に設定されており、入院時の食事代などを含めても手術にかかる自己負担は 10 万〜15 万円程度で済むことが多いです。現役並み所得者でも 30 万円前後に収まります。このように、日本では手術費用そのものが高額でも、自己負担額は制度によって一定額に抑えられています。
🇯🇵 日本の高齢者医療制度とワクチン費用
📊 公的医療保険と自己負担率
日本では全ての国民が公的医療保険に加入し、現役世代は医療費の 30% を自己負担します。70〜74 歳は原則 20%(現役並み所得者は 30%)、75 歳以上は 10%(現役並み所得者は 20%)です。入院・外来を問わずこの割合が適用されますが、高額療養費制度によって月ごとの自己負担上限が設けられています。標準的な所得層(課税所得 145 万円未満)の 70 歳以上では月 18,000 円、年間では 144,000 円が上限です。2025 年 8 月からは所得区分に応じて上限額が引き上げられました。高所得層では月 80,100 円+(医療費−267,000 円)×1% という上限があり、1 年間で数十万円の自己負担となります。
💉 ワクチン費用 – インフルエンザと帯状疱疹
日本では定期接種となっているワクチン以外は全額自己負担が原則です。成人のインフルエンザワクチンは 1 回接種が基本で、医療機関によって料金は異なりますが 自費接種で 3,000〜5,000 円程度 が相場です。自治体が補助を行うケースもあり、横浜市では 65 歳以上に対して 2,300 円の自己負担で接種できます。
帯状疱疹の予防には、生ワクチンと組み換え型ワクチンがあります。より効果が高いとされる 組み換え型ワクチン「シングリックス」 は 2 回接種が必要で、一般に 1 回 20,000〜30,000 円と高額です。横浜市では公費助成が行われており、1 回 10,000 円の自己負担で 2 回接種 できる制度があります。助成期間外は 1 回 23,000 円程度となり、2 回で約 46,000 円かかります。生ワクチンの方は助成がある場合 1 回 4,000 円程度(横浜市の場合)です。
👨⚕️ 医師の給与と勤務時間 – 日米韓比較
🇯🇵 日本の医師
日本の医師は高収入と言われることがありますが、実態は必ずしも恵まれているわけではありません。あるシミュレーション研究では、病院勤務医の平均年収は約 1,461 万円 と報告されています。年齢別には 20 代で 800 万円台、30 代で 1,100 万円台、40 代で 1,500 万円台、50 代で 1,700 万円台と上昇しますが、民間企業の同世代と比べて突出して高いわけではありません。外科医全体の平均年収も 1,374 万円ほどであり、心臓血管外科医でも 1,000〜2,000 万円台が多いとされています。
勤務時間も長く、2019 年の全国調査では 約 40% の医師が週 60 時間以上、10% 以上が 80 時間以上働いていました。2022 年の調査でも常勤医師の平均勤務時間は週 50.1 時間で、20% を超える医師が年間時間外労働 960 時間(週換算 18.5 時間)を超えていました。新しい働き方改革では時間外労働を年間 960 時間以下に抑えるよう求めていますが、夜間や休日の救急対応が多い医師にとっては依然として長時間労働が常態化しています。
🇺🇸 米国の医師
米国の医師の平均年収は約 30 万ドル(1 ドル = 147.96 円換算で約 4,439 万円)と日本の 3 倍近くに上ります。心臓外科医や整形外科医は 40 万〜50 万ドル以上(約 5,919 万〜7,398 万円)を稼ぐ場合もあります。にもかかわらず、米国の医師の平均勤務時間は週 50 時間前後と報告されています。専門によっては 60 時間を超えますが、日本ほど長時間労働は一般的ではありません。高い報酬は高い保険料や税金、そして国全体の医療支出の多さに支えられており、患者の窓口負担が少額でも医師の給与を維持できる仕組みになっています。
🇰🇷 韓国の心臓血管外科医
参考までに、韓国の心臓血管外科医の給与も見てみましょう。国際的な給与調査データによると、韓国の心臓血管外科医の平均年収は 2 億 2,171 万 4,807 ウォン、年収範囲は 1 億 3,081 万 1,736〜3 億 4,321 万 4,522 ウォンです。2025 年 9 月 30 日時点の為替レートである 1 ウォン = 0.10532 円で換算すると、平均は約 2,331 万円、範囲は 約 1,378 万〜3,614 万円 となります。この数字は日本の外科医よりやや高いものの、米国の医師よりは低い水準です。
⚖️ 医療費負担が異なる理由
米国では医師の給与が高くても、メディケアやメディケイドなどの公的保険制度により患者の窓口負担が低く抑えられています。国全体の医療支出が大きく、2022 年の 1 人あたり医療費は米国が約 12,400 ドルに対し日本は約 3,900 ドルと 3 倍以上の差があります。このため、高額な医療費を保険料と税金でカバーし、患者負担を減らすことが可能です。
一方、日本では医療費の自己負担額が抑えられている背景に、国民皆保険制度のもと社会保障費や税金が投入されていることがあります。診療報酬は低めに設定されており、その分を社会全体で支えることで患者の窓口負担を一定の割合に抑えています。政策側は財政支出削減のため税金補助を減らし窓口負担を引き上げる方向を議論しています。高齢患者の受診頻度の多さを問題視する声もありますが、その背景にはフリーアクセス制度などの構造的な要因があるため、単に医療費の自己負担を増やすだけでは問題の解決になりません。制度設計と財源規模の違いを踏まえ、医療費負担のあり方を慎重に考えることが重要です。
💡 結論
オレゴン州のメディケア・アドバンテージを利用する高齢者は、ワクチン接種や診療費、さらには冠動脈バイパス手術においても自己負担がごくわずかで済みます。日本でも高額療養費制度により手術費は抑えられますが、ワクチンや外来診療では 1〜3 割の自己負担が続きます。日本の医師は長時間労働であるにもかかわらず報酬が抑えられ、患者もワクチンや定期的な外来診療で既に多くの自己負担を強いられています。
政策的には、社会保障費や税金を削減するために「自己負担が低いので受診頻度が高すぎる」「医師の報酬が高すぎる」といった声が挙げられ、窓口負担の引き上げや診療報酬の抑制が議論されています。しかし、医療費の自己負担額が抑えられているのは社会保障費と税金が投じられているためであり、医師給与の多寡が財政を圧迫しているという主張は誤りです。現場で働いていた私の実感として、医師の報酬は長時間労働に見合わない水準であり、これ以上の報酬抑制や窓口負担引き上げは医療の質を損ねかねません。受診頻度の多さにはフリーアクセス制度などの構造的な要因があり、単純に負担を増やしたり報酬を削減したりしても問題は解決しません。持続可能で質の高い医療を守るためには、制度設計と財源のあり方を丁寧に議論する必要があります。