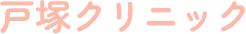2025/10/07
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
🩺【続報】週刊文春「高齢者が避けたい2種類の降圧剤」を読んで ― 本当に怖いのは“誤解”です
「とうとう出たね」
松本人志さんは別の意味でこの言葉を使っていましたが、
医療の世界にも、思わず同じ言葉を口にしたくなる瞬間があります😅。
📱LINEニュースに流れてきた見出し――
「高齢者が避けたい降圧剤、ついに判明!」
3行読んだところで“続きは購入で読めます💰”の一文。
……そう、やっぱり“売るための記事”なんです。
前回のブログ(👉 🧠 マスコミに騙されない!降圧剤・スタチンの真実)でも書きましたが、
週刊誌は昔から「血圧」「コレステロール」といったワードを、
ほぼ定期的に“恐怖と安心のループ”で取り上げます。
つまり、医療ではなく、マーケティング構造としての“高血圧”。
そして今回も、思わずつぶやいてしまうんです――「とうとう出たねぇ……」。
今度は週刊文春(2025年10月2日号)が
【高血圧の最新常識2025】「高齢者が避けたい“2種類の降圧剤”」という刺激的なタイトルで記事を出しました。
見出しだけを見ると、「危ない薬を教えます💣」という雰囲気。
でも――本当に怖いのは、薬そのものではなく、“誤解”の方です。
🧾 1.ガイドライン改訂=「高齢者にも厳しく」? 本当にそうでしょうか
文春記事では、日本高血圧学会の新ガイドラインで
「75歳以上の降圧目標が10mmHg引き下げられた」と紹介し、
あたかも“高齢者にも若者並みの血圧を求める時代”が来たかのように書かれています。
しかし、その理解は極めて表面的です。
確かにガイドライン上では、
75歳以上も「130/80mmHg未満」と数値が統一されました。
けれども、これは「目安」であって全員がそこを目指すべきとは書かれていません。
実際の本文を読むとこう書かれています👇
「高齢者では、全身状態・フレイル・認知機能を考慮し、柔軟に降圧目標を設定すること」
つまり、「高齢者にも厳格降圧」というのは誤読です。
むしろガイドラインが示しているのは、“個別化”の重要性。
数値ではなく、生活の質と安全性を守る降圧こそが目的。
文春記事は、この条件文をカットしたうえで「厳しすぎる」と結論づけており、
読者が“ガイドライン=高齢者いじめ👴💢”と誤解しかねません。
──実際の現場では「数字より生活」。
ガイドラインの真意は、“柔軟に対応しましょうね”ということなんです。😌
🧠 2.「厳格な血圧管理は認知症リスクを上げる」? ― データの文脈が違います
記事では、名古屋学芸大学の下方浩史教授が
「高齢者では血圧を下げすぎると認知症リスクが上がる」
とコメント。
…はい、ここだけ読むと「血圧下げたらボケるの!?😳」って思いますよね。
でも実際の研究データを開くと、文脈がまったく違います。📚
欧米の複数の研究(SPRINT MIND など)では、
-
血圧を適正に下げた群では脳卒中・心不全・腎不全が減少
-
過剰に下げすぎた(上が110mmHg以下など)群でリスク上昇
つまり、問題は「降圧」ではなく「過降圧」。
高齢者では血管の柔軟性が低下し、下げすぎると脳血流が減って“ぼーっとする・転倒する”などの副作用が出やすくなる。
要は、**ちょうどいい塩梅(あんばい)**が大事ということです。🍵
当院でも
「130を切ること」よりも「ふらつかない」「笑って食事できる」
――このほうがずっと大事。
血圧はテストの点数じゃありません。
日常を支えるバランスの話です。
💊 3.「避けたい2種類の降圧剤」? ― 医師の立場から見る真実
さて、問題の「2種類」。
💧 サイアザイド系利尿薬
❤️ β遮断薬。
記事では“高齢者が避けたい薬”とされていますが、
実はどちらも**「命を守る実績のある薬」**です。
十把一絡げに“危険”とするのは、ちょっと極端すぎます。💦
🧪 サイアザイド系利尿薬 ― 「避ける薬」ではなく「実績ある薬」
サイアザイド系は、体の余分な塩分と水分を尿として排出し、
血圧を下げる昔ながらの薬です。
「利尿薬」と聞くと“脱水しそう”というイメージを持たれがちですが、
実は世界で最も長く使われ、確かなエビデンスを持つ降圧薬の一つです💪。
代表的な臨床研究では、
-
SHEP試験(米国・平均72歳):クロルタリドン群で脳卒中36%減少
-
HYVET試験(欧州・80歳以上):インダパミド群で全死亡率21%減少
――と、いずれも高齢者で明確なベネフィットを示しました。
もちろん副作用(低ナトリウム血症・尿酸上昇など)は注意が必要。
しかし、それは「モニタリング不足」であって、「薬が悪い」わけではありません。
日本老年医学会のBeers基準にも
「定期的な電解質・腎機能チェックを行えば使用可」
と明記されています。
つまり「高齢者に禁忌」ではなく、
“注意して使えば最良の選択肢”。
サイアザイドはまさに、**“扱えば光るベテラン選手”**なのです⚾。
💊 β遮断薬 ― 使い方を誤れば危険、しかし本来は“命を救う薬”
β遮断薬は心臓の拍動を抑え、酸素消費を減らすことで心筋を守る薬。
心不全・不整脈・心筋梗塞――あらゆる現場で使われる命のブレーキペダルです🚗💨。
欧米の大規模試験(MERIT-HF, COPERNICUSなど)では、
カルベジロール・ビソプロロール・メトプロロールなどで
死亡率30〜35%低下、再入院も減少。
「避けたい薬」どころか、むしろ
“使わなければならない薬” です。
ただし――ここで大切なのは、
「正しい知識を持った医師が、正しく使うこと」。
β遮断薬は導入や増量のタイミングを誤ると、
脈が落ちすぎたり、心不全を悪化させるリスクがあります。
しかし、心機能・脈拍・症状を確認しながら少量から調整していけば、
むしろ最も信頼できる薬になります。
正しい理解と適切な管理のもとで使えば、
β遮断薬は**「安心して使える命の薬」**です。
🫀 心不全治療は“Fantastic 4”の時代へ!💥
かつては「三本柱」と呼ばれていましたが、
現在の標準治療は**4つの柱(Fantastic 4)**です。
それぞれがヒーローのように、異なる角度から心臓を守ります🦸♂️🦸♀️🦸♂️🦸♀️。
|
🧩 薬の分類 |
代表薬 |
主な作用 |
略語・解説 |
|---|---|---|---|
|
🩸 RAS系阻害薬(ACE阻害薬/ARB/ARNI) |
エナラプリル・バルサルタンなど |
血管を拡げ、心臓への負担を減らす |
RAS=Renin-Angiotensin System(レニン-アンジオテンシン系) |
|
💓 β遮断薬 |
カルベジロール・ビソプロロール |
交感神経を抑え、心拍数を下げる・寿命を延ばす |
β=β受容体(心臓のアクセルにブレーキ) |
|
💧 SGLT2阻害薬 |
ダパグリフロジン・エンパグリフロジン |
体内の余分な水分・糖を尿として排出し、心臓のうっ血を減らす |
SGLT2=Sodium-Glucose Cotransporter 2(ナトリウム・グルコース共輸送体2) |
|
⚡ MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬) |
スピロノラクトン・エプレレノン |
カリウム保持・線維化抑制で心臓のリモデリングを防ぐ |
MRA=Mineralocorticoid Receptor Antagonist |
これら4剤を適切に組み合わせることで、
心不全による死亡率・再入院率を大幅に下げることが実証されています。
💬つまりβ遮断薬は、「Fantastic 4」の一員。
「単なる降圧剤」ではなく、心臓チームの主役の一人なんです!🔥
❤️ 戸塚クリニックより ― 誤解より怖いのは“独断”
当院では、サイアザイド系利尿薬もβ遮断薬も、
開始前の血液検査・脈拍評価・用量調整を徹底。
一人ひとりに合わせた**“パーソナル降圧戦略”**を行っています。🎯
「降圧剤をやめたい」「でも脳卒中は怖い」――
その間の迷いを整理するのが、かかりつけ医の役目です。
薬は敵ではありません。
誤解と独断こそが、真のリスクです。
📱 そして今回、LINEで流れてきたあの記事
3行読んだところで“続きは購入で読めます💰”と出てきたあの記事。
結局、買って読む前に、診察で相談した方が早いです👨⚕️。
医療の真実は、記事の裏ではなく、あなた自身の体の中にあります。
そのサインを一緒に読み解く――それが、私たちの仕事です。
🩷「とうとう出たね」――その言葉を、
“誤解”ではなく“正しい理解”のほうに使える世の中へ。🌸