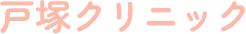2025/10/08
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
🏥 医療DXの正体:現場に押しつけられる“デジタル化コスト”
― オレゴン州の電子医療システムから見える、日本の構造的問題 ―
🌲 序章:またオレゴンの話です
このブログをお読みいただいている方なら、私の「オレゴン愛(Oregon Love)」はすでにご存じかもしれません。
今回もオレゴンを題材にしますが、自然やカフェ文化の話ではありません。
焦点は、「なぜオレゴンが今、アメリカ社会の焦点になり続けるのか」という点にあります。
2025年10月 ― 再び全米が揺れた
2025年10月、全米で緊張が走りました。
トランプ大統領がオレゴン州ポートランドでの抗議活動を理由に州兵の派遣を指示。
しかし、オレゴン州の要請を受けた連邦地裁(オレゴン地方裁判所)が一時差し止めの仮命令を出し、
権限行使の適法性が争点となりました。
カリフォルニア州のニューサム知事は声明で、
「これは公共の安全のためではなく、権力の誇示だ」と厳しく批判。
単なる政治ニュースにとどまらず、「なぜポートランドが標的とされやすいのか」という問いが浮かび上がります。
🏙 なぜポートランドなのか
ポートランドは、全米でも指折りの先進的でスマートな都市です。
環境への配慮、リベラルな価値観、LGBTQ+への包容、
医療・教育・起業文化の多様性が自然に共存しています。
経済効率よりも、暮らしの質と文化の厚みを優先する街づくり。
その姿勢が時に保守層から“極左的”と誤解されるほど、
価値観の自由度が高い都市でもあります。
興味深いのは、そのポートランドの都市思想――
「まちは人によって育ち、人がまちに育てられる」という感覚が、
いま世界中の都市計画者に静かな影響を与えていることです。
日本でも近年、この街の考え方に共鳴し、
新しい都市のあり方を模索する動きが始まっています。
なかでも、日本の大手デベロッパーの中で唯一、ポートランドに進出しているのが野村不動産です。
同社がこの地を選んだ背景には、単なる海外投資ではなく、
“人と都市の共生”という価値観への共感が感じられます。
それは、街の仕組みや制度よりも、
そこに暮らす人々の考え方や文化の成熟を大切にする姿勢です。
医療の現場に立つ私も、こうした“人を中心に考える”ものの見方には、
どこか通じるものを感じます。
🌐 この革新性が、医療DXにも通じている
実は、ポートランドを擁するオレゴン州は、
全米でも最も進んだ医療情報ネットワークを構築した州のひとつです。
その背景には、まさにこの街が培ってきた「自由で協働的な発想」があります。
行政・民間・医療機関が垣根を越えてデータを共有し、
人を中心にシステムを設計していくという姿勢――
それこそがオレゴンの医療DXを、全米屈指の先進システムへと押し上げました。
🇺🇸 政治が揺れても、医療は止まらない ― オレゴンの“構造としての強さ”
オレゴンでは、いくつもの医療情報システムが互いにつながっています。
EHR(Electronic Health Record:電子カルテ)は、患者の診療記録をデジタルで一元管理する仕組み。
PDMP(Prescription Drug Monitoring Program:処方薬監視プログラム)は、薬の重複処方や過量投与を防ぐため、州全体で処方履歴を共有。
EDIE(Emergency Department Information Exchange:緊急部門情報交換システム)は、救急搬送や入院の情報を関係医療機関にリアルタイムで通知。
POLST(Physician Orders for Life-Sustaining Treatment:終末期治療指示書)は、患者本人の意思に基づく治療方針を記録し、救急現場でも尊重される仕組みです。
これらの情報がすべてネットワークで連携しており、
どの病院でも必要なときに正確なデータを共有できます。
つまり「誰かの命を守るための情報」が、無駄なく流れる仕組みになっているのです。
🧩 仕組みの中身:制度・技術・文化の三層連携
- 政策基盤(Policy):州政府が主導し、未導入施設のEHR導入支援とデータ共有ルールの標準化を推進。
- 技術基盤(Technology):PDMP統合により、EHR・薬局・救急部門・保険者がワンクリックで処方履歴を参照可能。
- 文化基盤(Culture):データを「管理する」のではなく「共有して命を守る」という共通意識。
🩺 日本が学ぶべきこと
日本に必要なのは、特定のメーカーに縛られない、共通ルールの電子カルテづくりです。
どの病院でも、同じ形式でデータを扱えるようにすること――それが基本になります。
そのための国際的な仕組みが、HL7 FHIR(エイチエルセブン・ファイア)という標準方式です。
また、公開API(アプリケーションをつなぐ“共通の入り口”)を整えることで、
異なるシステムや機器どうしがスムーズに連携できるようになります。
さらに大切なのは、医師やスタッフが複数の画面を行き来しなくていい設計。
処方内容、検査結果、登録データ(レジストリ)などが、
ひとつの電子カルテ画面でワンクリックで見られるようになれば、
現場の負担は大きく減り、患者への対応にも集中できます。
別のタブを開いたり、別のIDでログインしたりせずに済む――
電子カルテの中で完結できることこそが、“本当に使えるデジタル化”の第一歩です。
💡 提言:日本の医療DXを「現場の道具」に戻すために
- 共通規格の採用:ベンダーに依存せず、HL7 FHIR準拠と公開APIを整備する。
- 電子カルテ内で完結:電子処方・検査結果・レジストリをワンクリックで参照できる設計に。
- リアルタイム通知型の運用:EDIEのように、来院・入退院・リスク検知を即時に共有。
- 公的コンソーシアムの常設:日本版HIT Commonsとして、補助金・API管理・監査・脆弱性対応を統合。
- コスト中立の制度設計:導入支援・維持補助・診療報酬加算を整合させ、現場が赤字にならないDXへ。
✍️ 終章 ― 日本の医療DXが変わる日
政治が荒れても、オレゴンの病院は止まりません。
データが流れ、医師が動き、患者が守られる――それは“構造としての強さ”があるからです。
日本も、「国のシステムを待つ」から「現場が選び、国が支える」へ。
医療DXが負担ではなく希望になるよう、設計の軸を“つなぐこと”へ戻しましょう。
追伸:オレゴンに惹かれる理由は、医療の合理性と人へのやさしさが、街の文化と同じ文脈で育っているからです。
あなたも、そろそろオレゴンを訪れたくなってきましたか? 🌲✈️