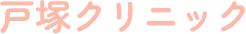2025/10/09
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
🧠 アセトアミノフェンと自閉症 ― トランプ大統領の“流行病”発言を受けて考える、診断の広がり
🔗 参考記事(New York Times, 2025年10月1日)
Families of people with severe autism say the repeated expansion of the diagnosis pushed them to the sidelines.
By Azeen Ghorayshi, The New York Times
🗞️ トランプ大統領は「自閉症の急増は前代未聞の公衆衛生上の危機だ」と発言し、
その原因として“ワクチン”や“アセトアミノフェン(解熱鎮痛薬)”を名指ししました。けれども現場で患者さんやご家族と向き合うと、そこには「数字」では測れない現実が見えてきます。
🧩【続編】自閉症は本当に“増えている”?
📖 前回のブログ「妊娠中のアセトアミノフェン使用と自閉症の関連について」では、
「薬の影響よりも、むしろ“診断の広がり”が自閉症増加の背景にあるのではないか」という視点をお伝えしました。今回はその続編として、New York Times の報道を手がかりに、“増えた”ように見える自閉症の実像と、その陰で見えにくくなった現実を考えます。
🧠 自閉症は本当に“増えている”のか
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の報告によれば、2000年には「150人に1人」だった自閉症の診断率が、現在では 「31人に1人」 にまで上昇しています。
数字だけ見れば“流行”のようですが、多くの専門家は次のように説明します。
「自閉症が増えたのではなく、診断の範囲が広がったのです。」
かつて“内気”や“個性的”とされていた人々が、現在では「自閉症スペクトラム」として診断を受けるようになったのです。
📰 NYタイムズが伝えた「もうひとつの現実」
2025年10月1日付 New York Times では、診断の拡大の影で取り残されつつある“重度自閉症”の家族の現実が描かれていました。
登場するのは、28歳の女性ジョディーさん。ほとんど言葉を話せず、食事や排泄など生活のすべてに介助が必要です。
「イーロン・マスクやビル・ゲイツのような成功者が“自閉症スペクトラム”として語られる時代になった」
― それは、かつて“ごく一部の重度障害”だった自閉症という診断が、いまや社会のあらゆる層に広がったことを象徴しています。
しかしジョディーさんの母親であり、米国自閉症科学財団(Autism Science Foundation)の代表アリソン・シンガー氏はこう語ります。
「イーロン・マスクと私の娘が同じ“自閉症”という診断なのは信じられない。」
診断の幅が広がることで、最も重い障害を抱える人たちが見えづらくなっている現実があるのです。
🧩 「Profound Autism」― 新しい区分の提案
こうした背景から、アメリカでは「Profound Autism(重度自閉症)」という新たな診断区分を設けようという議論が始まっています。これは「線を引く」ことではなく、最も支援を必要としている人に光を当てるための試みです。
しかし一方で、「分けることが差別につながるのでは」という懸念もあり、議論は今も続いています。
🩺 医師として、そして人として
私はこれまで、重度の自閉症のお子さんを育てるご両親を、何度も診察室で迎えてきました。診ているのは子どもさん本人だけではありません。支え続ける親御さん――特にお母さん・お父さん――の心の重さを、日々の中で感じています。
“自閉症”という言葉の下には、教科書では語りきれない、日々の静かな闘いと深い愛情が息づいています。
🚐 あの日の訪問、そして今年もその日がやってくる
医師として日々多くの患者さんを診る中で、障がいのある方やそのご家族と接する機会も少なくありません。けれども、実際にその「生活の現場」に足を運ぶことは、いままで一度もありませんでした。
そんなある年、障害者入居施設からの依頼で、ワクチン接種の出張に協力することになりました。診療所の外に出て、施設に暮らす方々と直接向き合う――それは、私にとって初めての経験でした。
初めて障害者施設を訪れたのは、数年前のワクチン出張のときでした。会場は施設の食堂。長机が並び、職員の方が利用者を一人ずつ連れてきて接種を行います。
そこには、本当にさまざまな人たちがいました。静かに腕を出す人、怖さから大きな声を上げる人、中には全身で抵抗し、職員が数人で支える場面もあります。
それでも職員の方々は、誰一人として動揺しません。「大丈夫」「もう少しだよ」と穏やかに声をかけ、まるで家族のように寄り添っていました。
「障害を支える」というのは、特別なことではなく、
“人が人を思いやる”という、ごく当たり前の営みなのだ――そう気づかされた瞬間でした。
そして、今年もまた、その訪問の日がやってきます。 あの日の記憶を胸に、私はまた、あの食堂でひとりひとりと向き合う時間を迎えます。
💬 共感という医療
診察室で、重度の障がいをもつお子さんのご両親と向き合うとき、私はあの施設の穏やかな時間を思い出します。言葉にならない想いや沈黙の奥に、どれほどの努力と優しさが積み重ねられているかを感じ取ろうとします。
医師としてできることは限られています。けれども、ほんのひとときでも、「自分たちはひとりじゃない」と感じてもらえるなら――それこそが、私にとっての医療の原点です。
🌱 最後に
NYタイムズの記事の最後で、母親のアリソンさんは、混乱する娘にこう語りかけていました。
「今日は“いつもの日”だよ」
どんなに過酷な日常でも、“いつも通り”の一日を守りたい。診断名よりも大切なのは、今日を安心して生きられること。私は、これからもその“いつも通り”を支える医療でありたいと思います。