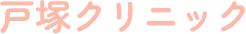2025/10/14
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
🍷【新展開】GLP-1は“やせ薬”を超えて ― アルコール依存症への新しい視点
2025年10月、米国内分泌学会誌 Journal of the Endocrine Society に興味深い総説が掲載されました。
(Srinivasan NM, Farokhnia M, Leggio L, et al. GLP-1 Therapeutics and Their Emerging Role in Alcohol and Substance Use Disorders. J Endocr Soc. 2025;9(11):bvaf141.)
内容は、肥満や糖尿病治療に使われているGLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)が、
アルコールや薬物依存症にも効果を示す可能性があるというもの。
これまで「食欲抑制薬」として知られてきたGLP-1が、脳と行動の領域にまで影響する――まさに“ホルモンの越境”を描いた論文です。
🧠 GLP-1が脳の「報酬系」に働く
GLP-1は腸から分泌されるホルモンですが、実は脳にもその受容体があります。特に延髄孤束核(NTS)や腹側被蓋野(VTA)といった領域で、GLP-1がドーパミン放出を調整し、“快楽”の過剰な興奮を抑えることが分かっています。
その結果、リラグルチド(Saxenda®)やセマグルチド(Ozempic®/Wegovy®)を投与した実験動物では、アルコールや甘味に対する“報酬”が低下し、摂取量が減少しました。脳科学的には、GLP-1が「食欲」だけでなく「快楽欲」も抑える神経ホルモンとして働く可能性が示唆されています。
🍺 アルコール依存への効果 ― ヒトでも兆しが
前述の総説によると、GLP-1RAがアルコール依存症(AUD)の新たな治療選択肢になり得ることが報告されています。
臨床試験では、週1回投与のセマグルチドによって「飲酒量」「飲酒日数」「飲酒衝動」がいずれも減少。さらに電子カルテ解析でも、GLP-1RA使用者はアルコール関連入院や再発のリスクが低下していました。
🚬 他の依存症にも? ― まだ“初期段階”
GLP-1RAはアルコールだけでなく、ニコチン、オピオイド、覚醒剤などの使用行動にも抑制効果を示した動物実験が報告されています。ただし、これらはまだ前臨床または小規模試験の段階であり、ヒトでの明確な有効性は確立していません。
特にオピオイド・ニコチン依存では、GLP-1が嫌悪反応や報酬回路の制御を担う可能性が指摘されており、「食べすぎ」「飲みすぎ」「吸いすぎ」が同じ脳回路で説明できる日も近いかもしれません。
💊 製剤の進化 ― 注射から「飲むタイプ」へ
| 製剤名 | 成分名 | 用法 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| ウゴービ® | セマグルチド | 週1回注射 | 肥満症治療薬として承認済。飲酒抑制効果を示した臨床試験あり。 |
| ゼップバウンド® | チルゼパチド(Tirzepatide) | 週1回注射 | GLP-1+GIPの“ダブルアゴニスト”。強力な体重減少効果。 |
| サクセンダ® | リラグルチド | 1日1回注射 | 古典的GLP-1製剤。アルコール摂取減少の動物実験データあり。 |
| オルフォグリプロン(開発中) | Orforglipron | 経口(飲み薬) | “飲むGLP-1”として注目。臨床試験では体重7〜11%減。未承認。 |
⚖️ 精神・行動への注意点
GLP-1RAは比較的安全性の高い薬剤ですが、一部報告では気分変化や希死念慮の出現など精神症状の変化が指摘されています。依存症を合併する患者では、服薬後の心理的変化を丁寧に観察する精神科的フォローが重要です。
🧩 報酬系ドミノ ― GLP-1がもたらす「理性のリマインド」
依存行動や過食行動の背景には、側坐核(NAc)―前頭前野(PFC)―扁桃体を中心とする「報酬系ドミノ」があります。これは、快楽刺激によりドーパミンが過剰放出され、理性のブレーキが効かなくなる連鎖反応です。
GLP-1はこのドーパミン・GABAバランスを調整し、「衝動→行動」の連鎖を穏やかにする――言い換えれば、脳の理性スイッチを再起動させる働きを持っています。
🌏 結びにかえて ― 戸塚クリニックから
GLP-1の話題を追っていると、医学って本当に“人間くさい”学問だなと思います。
食べすぎ、飲みすぎ、頑張りすぎ――どれも少し行きすぎた“人間味”の表れ。そして医療とは、その“行きすぎ”をちょっとだけ整えてあげる仕事なのかもしれません。
医者は、完璧な人間のためにいるわけじゃない。
「ちょっと疲れた」「最近なんか調子出ない」――そんなときに話を聞くのが、私たちの仕事です。
診察室では、体のデータももちろん大事ですが、「最近、何が一番しんどいですか?」という会話から始まることもあります。血圧より、心の圧が高いときもありますからね。
真面目な話も、くだらない話も、どちらもOK。軽い気持ちで来て、帰るころには少しホッとしてもらえたら――それが、私にとっていちばん嬉しい診療です。
“病院に行く”というより、“ちょっと話をしに行く”くらいの感覚で。
コーヒーを飲むように、気楽に医者を使ってください。
では次回の更新をお楽しみに!