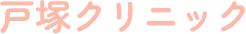2025/10/16
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
カレーと「リセット」と反ワクチン ― 戸塚の本屋で感じた“健康幻想”の香り
※本稿は医療・出版文化に関する公共的エッセイであり、特定の個人・団体への攻撃を目的としたものではありません。
戸塚の本屋で
令和7年10月16日(木)の昼。戸塚駅前の書店に立ち寄った。
入口近くの平台に『60歳でリセットすべき100のこと』が並んでいた。レジに並ぶ人の視線に自然と入る位置で、まるで香辛料のように配置されている“売れる本”の置かれ方だった。
著者は和田秀樹。精神科医、東大出身。『80歳の壁』『70歳が老化の分かれ道』『コレステロールは下げるな』など、どれも“医療の常識を優しく裏返す”タイトルが並ぶ。
今回は「60歳でリセット」。読者層を約20歳若返らせたのは、市場を読む嗅覚だろう。「高齢者向けネタの次は60代か」と思わず苦笑した。
ページをめくることもなく棚を離れたが、心にひとつだけスパイスの香りのような違和感が残った。
医療の“逆張り”はなぜ売れるのか
和田氏の著作を見渡すと、ある構造が浮かび上がる。それは「医療の常識を少し裏切りつつ、不安に寄り添う語り方」だ。
「血圧は下げすぎるな」「薬をやめる勇気」「医者に頼らない生き方」。どれも部分的には真実を含む。
しかし、本来は主治医が診察しながら慎重に判断すべき事柄であり、本やSNSだけを根拠に“薬を自己判断で中止してよい”という意味では決してない。
※薬の中止・変更は必ず主治医にご相談ください。
和田氏は精神科医であり、内科全般の専門家ではない。それでも「心の在り方が病を変える」という語りが読者を惹きつける。言葉ひとつで市場を動かす。その意味では、彼は極めて巧みなストーリーテラーでもある。
コロナ禍が残した「不信という感染症」
コロナ禍で広がったのはウイルスだけではなかった。もうひとつの感染症――不信である。
アメリカではワクチンが政治の象徴となり、日本では「副反応が怖い」「なんとなく信用できない」という曖昧な不安が静かに広がった。
そんな時代には、“医者が医療を疑う”という構図は実に魅力的に映る。「薬をやめよう」「検査を減らそう」「自然に任せよう」。こうした逆張りの言葉ほど、人の心の弱い場所に届いてしまう。
医療不信は刺激的で、そして――売れる。
「常識を疑え」の原点:近藤誠という始まり
この構造を最初に確立したのは、慶應義塾大学出身の近藤誠医師だ。
『患者よ、がんと闘うな』(文藝春秋, 1996)は、当時の標準治療に対する鋭い批判として大きな話題を呼んだ。
確かに、過剰治療が問題視された時代だった。しかし主張は次第に科学を離れ、信念の物語へと進んだ。報道では、彼の言葉を信じて治療を拒み、命を落とした人もいたとされる。
“慶應の医者が言うなら”という権威、“常識を覆す快感”――この二つが出版を支えた。そして今、その構造をより穏やかに再演しているのが、東大出身の和田秀樹氏だと私は感じている。
希望が商品になるとき
がんの標準治療を否定し、自然治癒・代替医療を推す語りは、今やひとつの“希望産業”になっている。
「副作用が怖い」「自然に治したい」。この純粋な願いこそが、最大の市場になる。
若くして亡くなった小林麻央さんのブログの一節、「できるだけ自然に治していきたい」は、本来“医療を補完しつつ前向きに生きたい”という思いだった。
しかし一部のメディアが文脈を歪め、彼女を“病院に頼らない象徴”として扱った。希望は時に商品化され、文脈は都合よく切り取られる。
※治療の適否は個々の病状で異なります。必ず主治医にご相談ください。
マザーテレサをどう引用するか
(※和田氏が実際にコルカタを訪問されたかどうかは、公知情報では確認できなかったため、表現を慎重に調整しています。)
和田氏の著作には、「心の在り方」や「死の迎え方」を語る章がしばしば登場する。その背景には、マザーテレサやコルカタのホスピス活動を想起させる文脈が見えることがある。
ここで重要なのは、引用の態度だ。
マザーテレサの言う「最も深い貧しさ」とは、“無関心でいられること”であり、「心を整えれば病が治る」といった自己啓発ではない。
彼女が示したのは、痛みに寄り添う“沈黙の勇気”であり、軽やかな人生論とは本質が異なる。
一方で和田氏の語りでは、テレサの思想が自身の人生観へ重ね合わせられているように映る瞬間がある。その結果、宗教的・哲学的な重い言葉が、自己啓発的メッセージへ読み替えられたように受け取れることがある。
偉人の言葉を借りることを否定しない。しかし、原典の重みと距離感を失ってしまえば、引用は容易に“装飾”へ変わる。その差は、沈黙を知る者と、言葉を扱う者の違いでもある。
出版バイアスというもう一つの薬害
学術界には「肯定的な結果が採択されやすい」出版バイアス(publication bias)がある。
健康本の世界ではこれがさらに強まる。「薬はいらない」「常識を疑え」「医者に頼るな」。こうした強い言葉ほど売れやすく、地味な科学が退屈に見え、派手な逆張りが真実に見えてくる。
これはもうひとつの薬害、情報の副作用だ。
医療は“疑う”でも“売る”でもなく、“共有する”
薬を減らすべきときもある。検査を見直すべきときもある。
だが、それを“思想”や“ブランド”にしてしまえば、医療は科学ではなく信仰になってしまう。
医療とは、リスクと希望を患者さんと共有する営みだ。断定ではなく、誠実な説明の積み重ねで成り立つ。
結び ― カレーの香りと健康幻想
レジ前の『60歳でリセット』を思い出しながら、街角のカレーの香りがふと鼻をくすぐった。
スパイスは心を温めるが、強すぎれば素材の味を覆い隠す。健康情報も同じだ。刺激が強すぎれば、科学の静かな味が消える。
カレーは体を温め、医療は人を守る。香りに酔わず、素材――確かな根拠と誠実な説明――を味わう感性を取り戻したい。
あなたは、どんな健康情報を“信じる”だろうか。
付記(改訂のお知らせ)
本稿の「マザーテレサと和田氏に関する記述」は、2025年11月20日、事実確認に基づき一部改訂しました。
改訂は「事実未確認の可能性がある箇所のトーン調整」を目的としており、文意・論旨は変更していません。今後も、より正確で誠実な医療・社会情報の発信に努めてまいります。
あとがき
今週はやや重い話題が続いたかもしれません。これは、北インド・アムリトサルを訪れた余韻が、まだどこかに残っているせいかもしれません。
来週は気分を切り替えて、医療の最新トピックをスクープ風にお届けします。
ほな今週もお疲れさまでした。ほんま、おおきに。