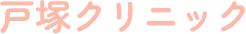2025/11/18
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
(参考)本記事は、米紙ニューヨーク・タイムズの報道 「AIに健康相談するアメリカの患者たち」 および、2022〜2025年に発表された主要20件以上の国際研究(BMJ、JAMA Network Open など)をもとに構成しています。 個人が特定される情報は含まず、日本の読者向けに内容を一般化しています。
ニューヨーク・タイムズ該当記事URL: https://www.nytimes.com/2025/11/16/well/ai-chatbot-doctors-health-care-advice.html
AI時代の健康相談:ニューヨーク・タイムズ報道から考える、AIチャットボットとの安全な付き合い方
■ はじめに
近年、健康相談のあり方が大きく変わりつつあります。
アメリカでは、 「まず医師ではなくAIに聞いてみる」 という行動が、若い方だけでなく高齢層にも広がっています。
ニューヨーク・タイムズ(New York Times)の報道では、AIが24時間いつでも返事をくれ、 どれだけ質問しても嫌な顔をせず、まるで自分の話を聞いてくれる相手のように振る舞う姿が描かれていました。
しかし同時に、緊急症状の見逃しや不正確なアドバイス、治療判断への悪影響、プライバシーへの不安など、 重要な問題も浮かび上がっています。
本記事では、NYTの内容と研究をふまえて、
- AIの「役立つ部分」
- AIの「危険になりうる部分」
- 日本の患者さんはどう安全に使えばよいか
- 医療者としての見解
を、できるだけ分かりやすくまとめました。
第1章:なぜアメリカでは「AI健康相談」が広がるのか
NYTの記事からは、アメリカ医療の 「アクセスの難しさ」 が伝わってきます。
● 医師の予約が取りづらい
専門医に数か月待ちということも珍しくありません。 その間に症状が悪化しても、すぐ診てもらえない現実があります。
● 診察時間が短すぎる
1回の診察が10〜15分程度と短く、患者さんが本当に聞きたいことまで辿りつけないこともあります。 「その話は次回で」「今日はここまでです」と区切られてしまうことも少なくありません。
● 医療費の高さ
1回の受診で数万円〜数十万円になることもあり、「少しなら我慢する」という選択が生まれやすい状況です。
● 心理的な距離の広がり
医師は忙しく、患者さんは「言いづらい」と感じる。 そのすき間を、AIが埋めるかのように登場しています。 こうした背景が、 「AIの方が丁寧に寄り添ってくれる」 という感覚につながっているようです。
第2章:研究が示す、AIチャットボットの「強み」
2022〜2025年にかけて多くの研究が行われ、AIが特に得意とする領域が見えてきました。
1)24時間アクセスできる
夜間や休日など、人がいちばん孤独になる時間帯に、AIは即座に寄り添ってくれます。 これにより「一人で不安を抱え込まなくて済む」という心理的な支えが生まれます。
2)症状の整理が上手い
AIは、
- 症状の棚卸し
- 考えられる原因の整理
- 次に取るべき行動の目安
を言語化するのが非常に得意です。 「何が不安なのか自分でもよくわからない」状態から、 「医師に伝えるべきポイントを明確にする」 という意味で、とても有用なサポートになります。
3)慢性疾患(日常管理)との相性の良さ
糖尿病・高血圧・脂質異常症などにおいて、AIは
- 服薬リマインド
- 食事や運動の記録
- 目標設定やモチベーションの維持
を手助けし、生活習慣の安定につながると報告されています。 医療者にとっても、「日々の記録が途切れない」ことは大きなメリットです。
4)軽度のメンタルヘルス支援
認知行動療法(CBT)的な会話は、AIが比較的得意とする領域です。
- 否定的思考の気づき
- 行動目標の整理
- 感情の言語化サポート
軽度の不安や落ち込みに対して、一定の効果が示されています。 ただし、重症の場合は必ず専門医の診療が必要です。
5)医療の事務負担軽減
AIが予約変更やよくある質問への対応、受診前の基本的な案内などを担うことで、 医療スタッフは診療により集中できます。日本の医療DXとも相性が良く、 今後の普及が期待される分野です。
第3章:一方で、見過ごせない「リスク」もある
このように多くの強みがある一方で、近年の研究や実際の事例からは、 決して見過ごせないリスクも明らかになってきています。
1)緊急性の判断が苦手
AIは、“危険信号”の見極めが不得意です。 例えば、次のような症状がある場合は注意が必要です。
- 強い胸の痛み
- 突然の息苦しさ
- 片側の手足が動きにくい
- 高い熱が続き、ぐったりしている
- 意識がもうろうとしている
こうした症状があるときは、AIに相談している時間はありません。 このようなときは、迷わず119番や最寄りの救急医療機関へ連絡してください。
2)自信満々に間違える
AIは「それらしい文章」を作るのが得意なため、内容が誤っていても非常に説得力を持ってしまうことがあります。 この点は多くの研究者が共通して指摘しているポイントです。
3)思い込みを強めてしまう
ユーザーが「きっと私はこの病気だ」と思い込んで相談すると、 AIがそれをきちんと否定できず、同調してしまうケースがあります。 本当は別の危険な病気が隠れていても、その思い込みが強化されてしまうリスクがあります。
4)プライバシーの不透明さ
アメリカではHIPAA、日本では個人情報保護法や医療情報のガイドラインが整備されていますが、 AIサービスのデータ管理はサービスによって差があります。 どこまで情報を入力するかは、慎重に判断する必要があります。
5)「人間としての全体像」が見えない
医師が診察で見ているのは文章だけではありません。
- 顔色や声の調子
- 歩き方や動作のスピード
- 受け答えのタイミング
- 胸やお腹の診察所見
- 過去の検査結果
- 家族構成や生活環境
こうした「非言語情報」を含めた総合評価こそが、医療の大切な部分です。 AIにはそれができません。ここは今後も、人間の医師の役割として残り続ける部分です。
第4章:実際に起きた「危険事例」
NYTの記事では、AIの助言を鵜呑みにした結果、次のようなことが起きかけた例が紹介されています (内容は一般化しています)。
- 誤った薬剤を摂取し、精神症状が悪化した
- 入院中の治療方針にAIの提案どおりの変更を求め、現場が混乱した
- 緊急性の高い症状が「様子見でよい」と案内され、受診が遅れそうになった
背景には、医療費の高さ・受診の難しさ・医師との対話不足など、構造的な問題が横たわっています。
第5章:日本では「AIと医師は競争しなくてよい」
日本は、
- 医療費の自己負担が比較的低い
- 初診でも専門的な診療につながりやすい
- 救急医療が全国に整備されている
という非常に恵まれた環境にあります。
そのため、日本ではAIが医師の代わりになる必要はありません。 むしろ、 「診察前の整理」や「診察後の振り返り」を助ける補助役 として使うことが、最も安全で効果的だと考えられます。
第6章:安全にAIを使うための「5か条」
1)AIは「情報整理」に使う
症状や不安をまとめる目的で使うと、とても有効です。 いつから・どんな症状が・何をしたときに強くなるか、などを整理しておくと、 診察の際にも大いに役立ちます。
2)病名の確定は任せない
AIの診断はあくまで“参考意見”です。 「この病名に違いない」と決めつけず、 「AIではこう出ましたが、実際はどうでしょうか」と医師に確認していただく方が、 結果的にも安心につながります。
3)緊急症状はAIより医療機関へ
危険な症状があるときは、AIより 119番・救急外来 が正しい選択です。
4)個人情報を入れすぎない
氏名・住所・家族の詳細など、余計な情報は入れない方が安心です。 どうしても入力する必要がある場合も、「ネット上に残る可能性がある」という意識を持っておくと安全です。
5)AIの回答をメモして受診するのは「とても良い」
AIから得た情報や整理した内容をメモして持参し、 「こういう説明をAIから受けました」「この点が特に不安です」と医師に伝えていただくことは、 診察をより質の高いものにしてくれます。 医療者側にとっても、患者さんの不安や疑問が明確になっていることは大きな助けになります。
■ 結び:AIは“医療を支える手段”、医師は“人を診る存在”
AIは、不安な夜にそっと寄り添い、症状の整理を助け、生活習慣の改善を支えてくれる頼れる存在です。
一方で、命に関わる判断や、複雑な全身状態の見極め、人生の背景に寄り添うケアは、 やはり人間の医師が担うべき領域です。
AIと医療は競うものではなく、 「AIで整理して、医師と相談して決める」 という協力関係を築いていくことが、これからの医療の理想的な形だと思います。
AIで調べてみても不安が残るようでしたら、いつでも私たちにご相談いただければと思います。