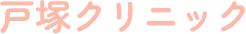2025/11/14
【横浜・戸塚駅西口 徒歩10分/駐車場あり】
内科・循環器内科・糖尿病内分泌内科|戸塚クリニック
(院長:村松 賢一)
当院は「内科のかかりつけ」として、
高血圧・糖尿病などの生活習慣病や体調不良、
甲状腺を含む内分泌のご相談まで幅広く対応しています。
予約優先制ですが、予約なしでも受診可能です。
(予約をおすすめする理由は待ち時間を短くするためです。
混雑時はお待ちいただく場合がありますが、症状に合わせて柔軟に対応します)
症状が気になる方は、ご都合のよいタイミングでお越しください。
▶ WEB予約(24時間受付)
https://wakumy.lyd.inc/clinic/hg08287
▶ クリニック案内
https://www.totsukaclinic.com
🍛 アムリトサルのランガルと日本の子供食堂・大人食堂
食卓が社会を支えるしくみとは
🌿 はじめに──診察室から見える「食べられない」というサイン
もし、あなたの目の前に、
「誰でも分け合える、あたたかい食卓」が広がっていたら──。
その場で誰かと肩を並べて座り、湯気の立つごはんを静かに口に運ぶ。
お皿の上には、特別なごちそうではなく、素朴だけれど心がほっとする料理。
──そんな食卓が、この世界には実際に存在しています。
診察室では、ときどきこんな声を耳にします。
「最近、きちんと食べられなくて……」
その小さなつぶやきの奥には、
その人の暮らしの状況や、社会のしんどさがにじんでいます。
仕事の不安、家計の苦しさ、孤立感、家族関係のストレス……。
「食べられない」という症状は、ときに心と社会が悲鳴をあげているサインでもあります。
一方で、世界には「誰でも座れる食卓」が、
何百年も途切れずに続いている場所があります。
インド・アムリトサルのランガル(無料食堂)、そして、日本各地で広がっている子供食堂・大人食堂です。
この記事では、私が2025年秋にインド・アムリトサルで体験したランガルと、
同じく2025年秋に報じられたアメリカのフードスタンプ(SNAP)危機とその正常化、
そして日本の子供食堂・大人食堂を重ね合わせながら、次のテーマを考えていきます。
「食卓のぬくもりが、人の心と社会の“免疫力”をどう支えるのか」
食卓は、心と体だけでなく、
「社会全体の免疫システム」にも関わる、大切な土台なのかもしれません。
🕌 アムリトサルのランガル
500年以上続く「誰でも座れる食卓」
2025年秋。私はインド北部・パンジャブ州アムリトサルにある、
シク教の聖地黄金寺院(Golden Temple)を訪れました。
そこで出会ったのが、シク教の無料食堂、
ランガル(Langar/ランガル=共同の食事)です。
現地で案内を受け、あらためて驚かされた基本情報は、次のようなものでした。
- 年中無休・24時間稼働
- 1日10万食以上が無料で提供される
(黄金寺院の案内資料や現地説明による、2024年時点の数字) - 宗教・国籍・性別・年齢・経済状況に関係なく、誰でも何度でも無料
- 豆カレー(ダル)、野菜のおかず、お米、チャパティなど、シンプルなベジタリアンメニュー
巨大な鍋でダル(豆料理)がぐつぐつと煮立ち、
チャパティ生地がローラーで伸ばされ、コンベアのように次々と焼き上がっていく。
長い広間にずらりと並んだ人びとが、床にまっすぐ座り、
同じお皿の上の同じ料理を、静かに味わっていました。
規模の数字だけでも圧倒されますが、実際にその場で調理や配膳の様子を目の当たりにすると、
「食べる」という営みが持つ力と、その場から立ち上がる“見えない安心感”という免疫を強く実感しました。
そこにいるのは、
- 地元の信徒
- インド各地・海外からの巡礼者
- 観光客
- 生活に困っている人
さまざまな人が、同じ床の上で、同じものを食べています。
この運営を支えているのが、1日およそ300〜400人のボランティア。
彼らはシク教でセヴァダール(Sevadar:奉仕者)と呼ばれる人たちです。
厨房で大鍋をかき混ぜる人、チャパティを焼き続ける人、
お皿を洗い、床を拭き、配膳をする人……。
広大なキッチン全体が、まるで巨大な家族のキッチンのように、無言の連携で動いている様子が印象的でした。
配膳をしていた20代くらいのセヴァダールが、私にこう語ってくれました。
「分け合うことは、祈りのひとつなんです」
私は見学のみで、実際の奉仕には参加しませんでしたが、
この言葉と、あの場の空気には、強い説得力がありました。
✨ シク教とランガルという仕組み
「誰も飢えさせない」が宗教そのものに刻まれている
シク教は、15世紀のインドで生まれた宗教です。
その核となる教えの一部は、次のようなものです。
- 万人平等(カーストや身分による差別の否定)
- 奉仕(セヴァ)
- 分かち合い(ランガル)
信徒は、収入の一部を寄進する
「ダスワンド(Dasvandh:十分の一の捧げもの)」という伝統を大切に守ってきました。
つまり、ランガルは、
「心優しい誰かが頑張って続けているボランティア活動」
ではなく、
「誰も飢えさせない」という価値観を、宗教と生活の中に“制度として組み込んだ仕組み」
なのです。
だからこそ、
- 施しではなく、「ともに食べる」という平等の実践
- 「してあげる/してもらう」という上下関係を、できる限り取り払う
- 「続けること」自体が信仰行為として尊ばれる
という文化が、500年以上にわたって受け継がれてきました。
ランガルは、
「慈善」ではなく、「共同体の免疫システム」として働いている、とも言えるかもしれません。
ランガルが「続いている」のではなく、
「続けることが信仰そのもの」だから止まらない。
アムリトサルのランガルを前に、私はそう感じました。
🇺🇸 2025年秋のアメリカとランガル
SNAP危機と、その後の正常化
同じ2025年秋、私はニュースを通じて、もうひとつの「食の不安」を目にしていました。
アメリカでは、予算をめぐる対立から政府閉鎖が長期化し、
低所得者向けの食料支援制度であるSNAP(Supplemental Nutrition Assistance Program)、いわゆるフードスタンプについて、
- 「11月以降、一部州で支給が遅れる、あるいは停止の可能性がある」
という報道が相次ぎました。
SNAPの対象者は、最大約4,200万人。
これは、日本の人口の約3分の1にあたります。
SNSには、
「冷蔵庫はほとんど空っぽ。SNAPが止まったら、子どもに何を食べさせればいいのか」
「貯金はほとんどない。明日からどう生きればいいのか」
といった投稿も多く見られ、
一時的に、深刻な不安が全米に広がりました。
しかし、その後の政治的な協議を経て、11月中旬に議会が正常化し、
最終的にはSNAPの支給は継続されることになりました。
「とりあえず明日の食事は守られた」という意味で、
低所得者コミュニティからは「ひとまず安心した」という声も聞かれます。
公的な制度が揺らぐとき、そこには一気に「社会の免疫力が落ちる瞬間」が生まれます。
SNAPの継続は、その免疫がなんとか保たれた、ぎりぎりのラインだったのかもしれません。
SNAP危機の中で動いたランガル
このSNAP危機の際、アメリカの複数のシク教寺院(グルドワーラ)が、
ランガルの提供体制を拡大したことが、いくつかの報道や現地コミュニティの発信から伝えられています。
たとえば、
- ニューヨーク
- カリフォルニア
- イリノイ
- テキサス
など、10州以上の地域で、
- 無料の温かい食事の提供
- パンやカレー、米などを詰めた食料パックの配布
- ドライブスルー形式での配給
といった支援が行われました。
コミュニティサイトやSNSでは、
「SNAPが止まりそうになったら、近くのシク教寺院へ。
ランガルは誰でも、無料で、何度でも食べられます」
といった呼びかけも共有されていました。
ある寺院について、複数の報道や現地コミュニティ情報によると、
責任者がこう話し合ったと伝えられています。
「お米が足りなくなったら、自分たちの家のお米を持ち寄ればいい」
「困っている人がいる限り、できるだけ24時間体制で支えよう」
政府の制度が大きく揺らいだとき、
「揺れない仕組み」として人々を支えたのが、このランガルだった、という側面があります。
そのうえで、最終的にはSNAPは維持され、
公的なセーフティネットと、宗教・コミュニティによるセーフティネットが、並走しながら人々の生活を支えた出来事
だったと言えるかもしれません。
※数値や記述は、2025年秋時点の報道および関係団体の発表などをもとにしています。
🇯🇵 日本の子供食堂・大人食堂
尊いけれど、まだ脆い「食の居場所」
日本にも、「誰でも座れる食卓」を目指す場所があります。
それが、子供食堂・大人食堂です。
認定NPO法人むすびえの2024年度の調査によると、
- 日本全国の子供食堂は10,866カ所
となり、全国の中学校数(約9,000校強)を上回る規模にまで広がっています。
大人食堂については、まだ正確な全国統計はありませんが、
各地で「おとな食堂」「誰でも食堂」「おとなり食堂」などの名前で広がりつつあります。
特徴を整理すると、
- 子どもの貧困や「孤食」を減らすことからスタート
- 無料〜数百円で、栄養のある食事と居場所を提供
- NPO・地域ボランティア・自治会・一部企業の支援で成り立つ
- 自治体や企業の補助もあるものの、全国一律の公的制度として位置づけられているわけではなく、多くは「任意事業」
といった点が挙げられます。
こうした取り組みは、日本の地域コミュニティの力を象徴する存在でもあります。
同時に、日本版の“社会的免疫”をどう育てていくかという挑戦でもあります。
一方で、現場では、
- 食材費の高騰
- コロナ禍の臨時補助金の終了
- ボランティアの高齢化・人手不足
- 会場(公民館・店舗・寺社など)の確保の難しさ
などの理由から、
「続けたいけれど、続けるのが本当に大変」という声も多く聞かれます。
同じくむすびえの調査によると、
子供食堂全体のうち、およそ1〜2割前後(約1,500カ所)が「活動不定期・休止・継続困難」と回答しており、
「来月も開けるかどうか分からない」
という不安を抱えながら続けている食堂も少なくありません。
それでも、ある子供食堂の運営者は、こう話してくれました。
「今日も一人でも、誰かが食べてくれたら、それで十分です」
この言葉には、アムリトサルで見たランガルのセヴァダールのまなざしと、同じあたたかさを感じます。
一方で、日本にはもうひとつ、見逃せない「見えない壁」もあります。
😔 日本にある「恥(スティグマ)」という見えない壁
子供食堂や大人食堂の聞き取り調査・現場の声を見ていくと、
しばしば出てくるのが、次のような言葉です。
- 「そこに行くと、『お金に困っている家』だと思われるのではないか」
- 「知り合いに見られたら恥ずかしい」
- 「子どもにも『恥ずかしい思い』をさせたくない」
ある保護者の方は、NPOの聞き取り調査の中で、こう打ち明けています。
「子どもが子供食堂に行きたがったけれど、
『お弁当を持ってきた』って、嘘をつかせてしまったことがあるんです」
日本では、「支援を受ける」という行為が、
本人の中で「負け」「みじめさ」「恥」と結びつきやすい文化があります。
そのため、
支援が一番必要な人ほど、利用をためらってしまう
という、深刻なジレンマが生まれています。
これは、子供食堂・大人食堂の善し悪しというより、
社会全体の価値観の問題です。
言い換えれば、
日本社会の「心の免疫」が落ちている部分が、そこに表れているのかもしれません。
🔍 ランガルと日本の食堂を比べて見える、3つの違い
ここで、アムリトサルのランガルと、日本の子供食堂・大人食堂を
「支えの構造」「参加の心理」「続いていく力」という3つの軸で比べてみます。
① 支えの構造
日本:善意のロープで支えられた「ロープの橋」
日本の子供食堂・大人食堂は、
- ボランティア・寄付・一部の補助金に支えられている
- 「やるかどうか」は、基本的に地域の人の善意次第
- 物価高騰や寄付の減少、担当者の退任などで、簡単に揺らぎやすい
という特徴があります。
私は、これを
「善意というロープで支えられたロープの橋」
だと感じています。
ロープの橋は、軽やかで、しなやかで、柔軟です。
しかし、ロープが細くなれば揺れ、切れてしまえば、橋ごと崩れてしまう危険もあります。
一方で、近年では、
- 企業との連携(フードロス削減とセットにした支援)
- クラウドファンディング
- 自治体との協定
などによって、橋脚を少しずつ太くしようとする取り組みも増えています。
ここに、日本ならではの「工夫の余地」と希望があります。
この工夫の積み重ねが、日本版の“社会的免疫”を育てる試みとも言えます。
ランガル:信仰と仕組みに支えられた「石造りの橋」
ランガルは、
- ダスワンド(収入の一部を寄進する伝統)
- セヴァ(奉仕)という信仰実践
- 寺院という「場」の存在
によって、宗教と生活そのものに組み込まれた仕組みです。
- 「やるかどうか」ではなく、「どう続けるか」が前提
- 危機のときほど「もっと支えよう」とエンジンがかかる文化
- 財源も、人手も、「信仰」として支えられている
この意味で、ランガルは
「信仰と制度が支える石造りの橋」
と言えるかもしれません。
同じ「橋」であっても、
- 善意が支えるロープの橋
- 信仰と制度が支える石造りの橋
その「揺るがなさ」の違いは、とくに危機の場面で大きく現れます。
石造りの橋は、社会全体の“長期的な免疫”を支えている構造にも似ています。
② 参加の心理
日本:スティグマ(恥)が利用の壁になる
日本の食堂には、「恥」の壁が立ちはだかることがあります。
- 「あそこに行くと、『貧乏だ』と思われるのではないか」
- 「子どもがかわいそう」
- 「自分が頑張ればなんとかなるはずだ」という自己責任感
こうした気持ちのために、
支援にアクセスすべき人ほど、足が向きにくい
という現象が、各種の調査や現場の声から見えてきます。
これは、心の中でゆっくり進む「免疫低下のようなプロセス」に少し似ています。
表面上は元気そうに見えても、内側ではじわじわと自己否定や孤立感が広がっていく。
そうした状態が続けば、社会全体としても免疫力が落ちていきます。
ランガル:助けを受けることが「当たり前の行為」になる
一方、ランガルは、
- 礼拝の後、そのままランガルホールに降りて食事をいただく
- 旅行者も、裕福な人も、生活困窮者も、同じ床に並んで座る
- 「寺院で食事をいただく」という行為そのものが、宗教文化として「当たり前」
という仕組みになっています。
そこには、
「行ったら貧しいと思われるかもしれない」
という感覚が、ほとんどありません。
「礼拝に来たついでに、みんなでごはんを食べて帰ろう」
「お腹が空いたから、寺院に寄ってランガルをいただいていこう」
という自然な流れのなかで、
助けを受けることが「普通の行為」として受け入れられています。
ここに、「同じ食支援」でも利用しやすさが大きく違う理由があります。
そして、この「参加のしやすさ」が、ランガルという仕組みの免疫力の高さにつながっているように感じます。
③ 続いていく力
日本:草の根ゆえの不安定さと、工夫の広がり
日本の子供食堂・大人食堂は、この10〜12年ほどで一気に広がった、まだ若い運動です。
- 「誰かのために」と始まった小さな活動が、全国に広がった
- しかし、担い手の高齢化・燃え尽き、資金の不安定さ、場所の確保の難しさと常に隣り合わせ
- 正確な統計はありませんが、数年で形を変えたり、休止に追い込まれる例も少なくない
まさに、
「素晴らしいけれど、ギリギリで踏ん張っている」
という表現が当てはまります。
それでも最近は、
- 自治体と連携した「公設民営」に近い取り組み
- 企業がフードロス対策として安定的に食材提供を行う例
- 学校・病院・医療機関との連携(栄養相談・健康チェック)
など、「ロープの橋」を少しずつ補強する動きも出てきています。
こうした工夫の積み重ねが、日本社会における「食の免疫ネットワーク」を作り始めているのかもしれません。
ランガル:500年以上“止まらない仕組み”
ランガルは、シク教の開祖グル・ナーナクの時代(15世紀末)から
500年以上にわたって続いてきたと言われています。
- 植民地支配
- 戦争
- 分離独立
- 政治的混乱
さまざまな歴史的激動の中でも、
「ランガルをやめる」という選択肢が真剣に議論されたことはほとんどありません。
2025年のSNAP危機でも、
「お米が足りなければ、信徒が家からお米を持ち寄ればいい」
「必要な人がいる限り、できるだけ24時間体制に近づけよう」
という姿勢が報じられ、実際に提供体制を強化した寺院もあると伝えられています。
危機が起きるほど、むしろエンジンがかかる。
ここに、ランガルという仕組みの「続いていく力」があります。
いわば、ランガルは、何世代にもわたって更新されてきた「宗教と共同体の長期免疫」なのだと思います。
🩺 医療者として感じること
食卓は、薬では届かない場所に効く
医療の研究データでも、「食卓」と「心の健康」の関係は、はっきりと示されています。
いくつかの日本の調査では、
- 孤食の子どもは、そうでない子どもに比べて、うつ症状が出るリスクが約1.8倍になる
(※うつ症状の発症リスクを約1.8倍に高める、という意味です) - 食事支援を受けた子どもは、自己肯定感が約20%高い
(※自己肯定感の尺度の得点が、平均で約20%向上した、という調査です)
といった結果が報告されています。
(日本子ども家庭総合研究所 2023年 などの報告より)
なぜ、孤食がつらさにつながるのか。
一人で食べる時間が増えると、
- 「自分はひとりなんだ」という感覚が強まりやすい
- 誰かに悩みを打ち明ける機会が減る
- 「どうせ自分なんて」という考えが、頭のなかでぐるぐる回りやすい
といった形で、社会的な孤立感が高まってしまいます。
これは、心の中でゆっくり進む「免疫低下のようなプロセス」に少し似ています。
表面上は元気そうに見えても、内側ではじわじわと自己否定や孤立感が広がっていく。
そうした状態が続けば、社会全体としても免疫力が落ちていきます。
逆に、誰かと一緒に食卓を囲むことは、
- 「自分はここにいていい」という安心感
- 何気ない会話、ちょっとした笑い
- 「おいしいね」「ありがとう」と言い合える関係性
を通じて、心の土台をじんわりと強くしてくれます。
医療者として診察室にいると、
- 「血圧を下げる薬」
- 「血糖を下げる薬」
だけでは届かない場所に、
食卓のぬくもりが確かに作用していることを感じる瞬間があります。
ランガルも、日本の子供食堂・大人食堂も、その根底で伝えているメッセージは、とてもシンプルです。
「人は、誰かと食べることで強くなる」
そしてそれは、個人の心だけでなく、
社会全体の免疫力にも、静かに効いていく作用なのだと思います。
🌱 あなたの街で、今日からできる一歩
ここまで読んでくださった方に、
「じゃあ、私は何ができるのか?」という問いが浮かぶかもしれません。
大きなことをする必要はありません。
今日からでもできる、小さな一歩を挙げてみます。
- 近くの子供食堂・大人食堂を知る
例:認定NPO法人むすびえの「全国子ども食堂マップ」など。
まずは地図上で、自分の街にどんな「食の居場所」があるのか眺めてみるだけでも一歩です。 - フードバンクや団体への食材寄付を検討する
お米1kg、缶詰1個、レトルトカレー1つからでも十分力になります。
家に眠っている「まだ食べられるけれど使う予定がない食材」があれば、立派な支援です。 - 家族や友人と、一緒に食べる時間を少し増やす
週に1回、10分でもいいので、「一緒にテーブルを囲む時間」を意識してみる。 - 気になるあの人に、「今度ご飯でもどう?」と声をかけてみる
それは、その人にとっての「一回分のランガル」になるかもしれません。
これらは、特別な資格も、大きなお金も必要ありません。
小さな一歩が、まわりの人と社会の“免疫力”を、少しずつ強くしていきます。
🧭 まとめ──食卓を失う社会は、免疫を失う
最後に、この記事のポイントを3つに整理します。
- 支えの構造
日本の子供食堂・大人食堂は、善意と寄付に支えられた「ロープの橋」。
草の根の力で広がってきた一方、脆さも抱えています。
ランガルは、信仰と制度に組み込まれた「石造りの橋」。
続けること自体が信仰行為であり、500年以上止まらず機能してきました。 - 参加の心理
日本では、「支援を受ける=恥」というスティグマが、利用の壁になることがあります。
そのため、支援を最も必要とする人ほど利用をためらうという課題があります。
ランガルでは、助けを受けることが礼拝の延長として「自然な行為」とされ、旅行者も富裕層も困窮者も、同じ床に座って同じものを食べます。 - 続いていく力
日本の食堂は、ここ10〜12年で急成長した若い運動であり、持続性を高めるための工夫が今まさに求められています。
ランガルは、歴史的な激動をくぐり抜けながらも、危機のたびに「もっと支えよう」と加速してきた、強靭な仕組みを持っています。
そのうえで、両者に共通しているのは、
「食卓のぬくもりが、人を強くする」
という、ごくシンプルで、しかしとても大事な真実です。
食卓を失う社会は、免疫を失う。
ランガルも、日本の子供食堂・大人食堂も、その免疫を少しずつ取り戻す“栄養剤”なのかもしれません。
この文章が、あなた自身の食卓を見つめ直すきっかけになり、
どこかの誰かの「一皿分の安心」につながることを、
医療者として、そして同じ社会を生きる一人として、心から願っています。